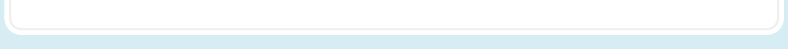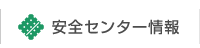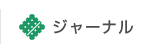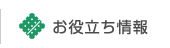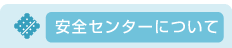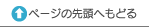北海道勤労者安全衛生センター トップページ > 安全センターについて > 2011年度活動計画
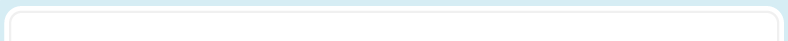
2011年度 活動の進め方
Ⅰ. 活動の基本
1. はじめに
(1)NPO設立の趣旨に沿った活動の強化
2010年(平成22年)は労災事故死亡者数が91名(12月末未確定)と前年に比べ激増(+22)しましたが、これは2009年が69名と前年に比べ大幅に減少した(-12)ことを考慮しても、2008年(平成20年)と比べて+10の増であり、特に道路貨物運送や林業で大幅に増加しました。
一方、今職場で最大の関心事となっているストレス・メンタルヘルス問題は、依然として深刻な状況にあり、雇用や生活への不安や、競争激化による業務上の過大な目標と各種のハラスメントなどで押しつぶされた労働者の「心」に関する労働災害にも目を向けなければなりません。
そのほか職場には、VDT(コンピュータ端末)による眼精疲労や、頸肩腕症候群などの上肢疲労障害、腰痛の蔓延、アスベスト被害の本格化など、業務に起因するさまざまな疾病・傷病とともに、ナノテクノロジーや新しい化学物質が新たな問題を提起しつつあります。また、最近注目されてきた「軽度外傷性脳損傷(MTBI)」や「化学物質過敏症(CS)」について調査・研究し、これらの労災認定を拡大する活動も求められています。
私たちは、労働災害の防止が、勤労者のいのちと生活を守り、雇用の安定と経済の活性化に寄与する基盤であると考え、NPO法人北海道勤労者安全衛生センターを設立いたしました。
NPO北海道勤労者安全衛生センターは、職場におけるOSHMS(労働安全衛生マネジメントシステム)の普及や、リスクアセスメントの取り組みなどを通じ、職場の安全衛生意識を定着させること。また、従業員のコミュニケーション能力を高め、風通しのよい職場環境を創造することことにより、メンタル不調者の発生を抑制することなどを通じ、第11次労働災害防止計画における北海道の目標達成に向け、各事業場における自主的な安全衛生推進諸施策の強化や、行政の提供する制度の活用に積極的な支援を行っていきます。
(2)メンタルヘルス対策の緊急対策
ストレス・メンタルヘルス問題は、精神疾患の年間受診者数が100万人に達するほど、深刻な状況となっています。その中で、職場におけるメンタルヘルス発症に関わり、精神障害に係る労災申請は全国で1千件を超えたものの、その約2割しか認定されず、多くが業務以外の起因や個体側要因に帰されて、労働者保護が行き渡っていません。
メンタル不全問題への対応は、従来のセルフケアやラインケアと言った対処的な取り組みから、「職場環境配慮義務(安全配慮義務に含む)」の観点にたって、一次予防と連鎖の防止を重点にした予防的取り組みへと変化させなければなりません。そのため、職場全体のストレス調査・点検の取り組みがますます重要になっており、また、労働基準法改正(2010.4.1)で強化された労働時間管理の徹底と過重・長時間労働の撲滅、産業医面談のあり方、さらには業務上外を問わす治療期間の補償ルールの明確化、円滑な職場復帰のための社会的なサポート制度とプログラム作成などを緊急に充実させる必要があります。また、各種ハラスメントの実態把握と職場環境の改善について、企業や官公庁の対処方針についても、助言と提案をすることが求められます。
現在、厚生労働省では「精神障害の労災認定の基準に関する検討会」、およびその「セクハラ分科会」で精神障害の労災認定について見直しを行っていますが、その議論を注視し、「いじめ防止法(仮称)」の早期制定を見据えた法整備を求める運動を強化する必要があります。
安全センターは設立の主旨である「職場の安全・衛生対策、健康増進、労災・職業病、環境保全対策等の調査、研究と予防対策等の活動」を使命として、「働く者の安全と健康を第一に」考え、実践していきます。
今後も会員各位と協力し、設立の原点を再確認し、職場で働く仲間の安全と健康確保など、職場の要望と期待に応える取り組みをさらに強化していきます。
2. 職場における安全衛生活動の活性化とネットワークの強化
「安全専一」のスローガンが掲げられ、我が国の労働安全運動が始められてから100年の時を迎えます。改正労働安全衛生法により「予防文化の普及」が求められ、労使の「責任ある自主的取り組み」がこれまで以上に重要となり、働く者の安全と健康確保は企業の責任においての実施を原則としつつ、安全衛生委員会の定例開催や活性化等について、労働組合にも大きな役割が期待されます。職場実態を一番よく知りうる労働組合が点検し、改善していく体制がなければ実効あるものにならないことも明らかです。
しかし、労働組合の役員任期が短くなる傾向があって、「安全衛生担当」の就任任期も短く、十分な知識と実践経験が育成されないことが悩みでもあります。より効率的な人材の育成プログラムと手法が求められています。
北海道勤労者安全衛生センターは、これらの活動に資するため、各種の労働安全研究機関、産業衛生学会、関係行政機関、産業保健推進センターなどとのネットワークに参加し、これらの連携のもとで、専門家の知識・智恵を吸収する機会を設定し、全道規模の研修会・担当者会議、地域健康セミナーなどの充実を図ってきました。
特に、連合本部の安全衛生活動方針に沿って、全国安全衛生センター連絡会を始め、各地の安全衛生活動や労働安全衛生・公衆衛生の向上を目的に活動する組織と連携し、研修会等への参加を通じて相互交流・情報交換を深めていくことが重要となっています。
3. 北海道医療生協・職業病センターとの連携強化と調査・研究活動の充実
職業病対策(腰痛・化学物質管理、VDT障害、振動病、じん肺やアスベスト問題等)についての継続した調査研究や、生活習慣病の予防の調査・研究と啓発活動などに取り組むため、北海道医療生協・札幌緑愛病院(会員)の「職業病センター」は、働く者にとって大きなよりどころとなります。医療のみならず予防の観点も含め積極的に連携し、労働者の健康を守る取り組みを一層強化していくことが必要です。また、「職業病センター」の全道における地域活動をサポートします。
職場におけるストレス・メンタルヘルス対策は依然として緊急課題となっており、今年度も日本産業カウンセラー協会北海道支部や、精神対話士・産業カウンセラー等の有資格者と連携し、職場におけるメンタルヘルス活動の充実をはかっていきます。
4. 地域や職場活動への貢献とホームページの充実
労働基準法、労働安全衛生法と関連する政令・省令・指針など、職場の安全衛生活動に必要な情報をタイムリーに提供するため、機関誌「安全衛生Journal」や報告書等の刊行物の発行、資料や教材の収集に努めます。
安全センターのホームページは、定期的な更新に努め、E-mailによる「北海道安全衛生センター情報」の継続的な発行に努めます。
Ⅱ. 具体的な活動目標
1. 調査・研究事業
(1)安全衛生活動に関する実態調査と安全衛生委員会の活性化調査
「連合労働安全衛生取り組み指針」に沿って、安全衛生委員会の未設置解消や委員会の活性化を進めるために、幅広く好事例を紹介するなど会員産別・団体や連合北海道の地域組織に役立つ資料・情報を調査し、積極的に提供して職場の安全衛生活動をサポートします。
連合の「第7回連合安全衛生に関する調査(2011年)」を参照しつつ、第11次防(労働災害防止計画)の目標達成に向けた安全衛生活動の進め方の検証や、労働組合としての問題意識、ストレス・メンタルヘルス対策やリスクアセスメント・マネジメントシステムの展開などの具体的課題について調査を実施します。
また、「非正規労働者の労働安全の実態調査」の第4回目として、連合北海道の非正規労働センターなどと連携した調査に取り組みます。
(2)労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)に沿った「POSITIVE」のトレーナーセミナーの開催
労働安全衛生リスクアセスメント・マネジメントシステム(OSHMS)は、職場の安全の向上とメンタルを含む衛生環境の向上に有効であるにもかかわらず、約半数の企業が実施しているに過ぎず、特に99人以下の事業所ではまだまだ普及率・理解率が低い状況です。今年度も(財)労働科学研究所・連合本部などと連携し、OSHMSを各職場段階で実践的な取り組みが出来るようにするための調査・実践研究に取り組みます。OSHMSを職場で実践するためのノウハウの一つとして、「PDCAサイクル」をベースとする取り組みが容易な「POSITIVE(労働組合主導の参加型安全衛生向上プログラム)」の職場トレーナー、コア・トレーナー育成に取り組みます。
(3)ストレス全数調査の事業化
精神疾患100万人受診時代を迎え、職場のストレス状況を把握することは緊急課題となっています。有効な「メンタルヘルス対策」を確立する上でも、簡易ストレス調査票を活用した「職場全数調査」や「アミラーゼ・テスト」など、実態把握の調査活動を活発化させ、組合員個人のストレス・プロフィールや職場全体のストレス傾向を明らかにし、1次予防の普及に努めるとともに、将来の事業化に向けた環境整備に努めます。
公務職場におけるストレス調査を、医療生協・札幌緑愛病院職業病センターと連携して実施します。
(4)労災保険制度の実態調査と審査請求のサポート
労災保険制度は、職場や通勤途上で災害にあった労働者の治療と生活、将来を保障する重要な制度ですが、業務上外の判断をする際の事実把握をめぐって、労働者保護の機能を十分果たしているとは言えません。特に「医証(医師の診断)」について、十分な証拠に基づく判断が常に出されているとは言い難く、その結果として業務外に起因するとされて不支給決定となり、雇用を失う例が後を絶ちません。
北海道勤労者安全衛生センターは、北海道医療生協・札幌緑愛病院(会員)の「職業病センター」と連携し、じん肺・アスベスト、振動病、メンタルヘルスに関する専門医を活用して、事実に即した労働者保護の労災保険制度を実現するため、実態調査に取り組みます。
また、最近注目されてきた「軽度外傷性脳損傷(MTBI)」や「化学物質過敏症(CS)」について調査・研究し、労災認定の拡大に資する活動を強めます。
2. 研修・セミナー事業
「団塊世代」の大量退職の一方で若年者の職場定着率の悪化や雇用の非正規化が進展し、職場の技術的な伝承が危機に瀕するとともに、「安全に関する技術と経験」が急速に失われています。今後も産別・地域の研修会やセミナーを通じ、安全衛生のレベル維持を目的とした研修の実施に努めます。
(1)第70回中災防全国産業安全衛生大会や連合全国セイフティネットワーク集会への参加
「安全専一」を掲げて労働安全運動が始められてから100年。その節目の「第70回中災防全国産業安全衛生大会」が10月12日に東京で開催されます。この節目に安全運動の歴史を俯瞰し、時代に応じた安全衛生活動の知識を習得する機会として、会員産別・団体をはじめ連合北海道地協にも広く呼びかけ、第70回中災防全国産業安全衛生大会に参加します。
また、連合全国セイフティネットワーク(SN)集会が6月27日に東京で開催される予定となっています。連合本部と連携して、全国SN集会の成功と、北海道の労働安全衛生レベルの向上に資する取り組みを進めます。
(2)全道研修会の開催
連合北海道と共催し、北海道ブロック・セイフティネットワーク集会と全道安全衛生研修会(担当者会議)を開催します。ともに現場視察など実践面を重視するとともに、知識の体系化と経験交流を含めた取り組みとなるよう努めます。
(3)安全・健康セミナーの開催
各地域における安全・衛生セミナーの開催について、連合北海道の地協等と協力して取り組みます。また、会員産別(単組)や会員労働福祉団体をはじめ、企業等のセミナー開催に助言とサポート、会員職場でのセミナー等への講師派遣に取り組みます。
また、労災防止指導員制度の廃止により地域の労働災害防止機能が低下しないよう、地協専従者や地協の担当者のスキルアップに努めます。
(4)ストレス・メンタルヘルス対策指導者の育成 (補助金事業)
精神疾患に関する知識の習得をはじめ、職場復帰プログラムの作成指導、産業医による面接指導や労働時間管理の徹底、法的な整理など、職場での取り組みに重点を置いた対策の充実をはかるために、日本産業カウンセラー協会北海道支部と連携して、職場における「メンタル対処指導者」の育成セミナーを開催します。
また、これら指導者育成に活用するため、メンタルヘルス問題の発見から治療・職場復帰・労災認定・精神疾患と法律など、トータルに理解するための資料「職場におけるメンタルヘルスの改善のために」を改訂・充実させます。
3. 相談・広報事業
(1)機関誌「安全衛生Journal」の発行等
安全センターの活動や調査・研究の結果などを掲載するとともに、法制度の改正や安全衛生に関するポイント解説面を充実させます。また、安全衛生や労働基準に関する最新情報や各県・他団体の取り組み等の情報を提供します。
ホームページの充実をはかり、定期的な情報の更新に努めます。また、「安全衛生センター情報(E-mail)」の継続発行に努めます。
(2)無料電話相談の充実 (補助金事業)
日本産業カウンセラー協会北海道支部と協力し、勤労者の相談しやすい「ストレス・メンタルヘルス無料電話相談」活動を充実・継続します。今年度は、フリーダイヤルを導入し、相談者の利便性を向上させます。
(3)資料、図書の収集と活用
安全衛生活動全般に関わる最新の資料や図書、ビデオなどの収集と更新を行います。また、各都府県安全センター、安全衛生活動団体等と刊行物の交流・交換活動を行います。
会員等への情報サービス機能を高め活用を促進するよう、所蔵する資料・図書類をリスト化し紹介していきます。また、VHSビデオをDVDに変更し、会員利用の向上を図ります。
4. 政策・制度に関する活動
調査・研究活動や相談活動などを通じて、労働安全衛生に関する政策・制度要求を掘り起こし、連合本部と連合北海道はもちろん、会員、地域、関係団体、医療機関などと連携して実現する活動に取り組みます。
特に、北海道医療生協・札幌緑愛病院職業病センターや北海道アスベストじん肺訴訟団の活動と連携し、アスベスト問題の理解促進と労災認定、救済制度の充実に努めます。
各種審議会委員、労災保険審査会参与との連携・連絡体制をつくり、労働行政への意見反映や行政情報の活用に取り組みます。
5. 会員拡大とネットワークの拡大
NPOの活動と体制を強化・充実するため、正会員、特別会員の拡大を進めます。
6. 全国安全衛生センター連絡会議第22回総会の札幌開催を支援更
全国各地の安全衛生運動における情報交換と経験交流をはかる「全国安全衛生センター連絡会議」の第22回総会が札幌で開催される予定になっています。
北海道における安全衛生のレベル向上の機会ととらえ、北海道医療生協・札幌緑愛病院職業病センターと連携して、総会成功のため支援活動に取り組みます。
以上